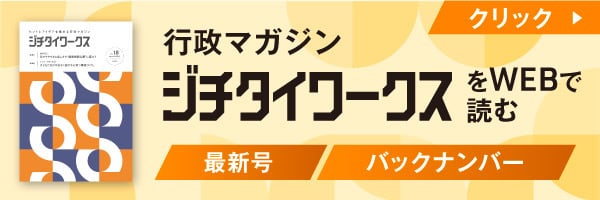初めての農業体験企画。その集客結果は……。
――佐藤さんは、どんな“しくじり”を経験されたのですか?
入庁後、最初に配属されたのは農業関連の部署で、農業後継者の協議会などを担当しました。
でも、農業については素人だったので、専門的な話は全く分からない状態。もどかしい思いをしながらやっていました。そんな中、3年目に農業体験講座を実施することになったんです。
早速、上司が地元の農業法人に協力を依頼し、体験希望者を受け入れることが決定しました。私はその法人とやりとりしたり、募集をかけたりと、実施に向けて準備を進めました。どれくらい人が集まるかな?という感じで。そうしてフタを開けてみると、集まった参加者は、2人という結果でした。

――お2人ですか!現場の様子はいかがでしたか?
その法人は野菜全般を大規模に生産していて、少人数だったのが余計に寂しく感じられました。私も上司も「最初だから仕方ないのかな……」と。参加者にも、ご協力いただいた法人にも申し訳ない気持ちでした。
それでも、1年サイクルの企画をスタートすることになりました。参加者のお1人は農業での自立を考えている方、もう1人は実家が農家という方でした。2人とも企画のイメージにぴったりだったのですが……、長い1年の始まりでした。
知見を深めるため、自身もイベントに参加。
――そもそも、なぜ人が集まらなかったのでしょう?
初めての試みだったこともありますが、やはり告知の方法に課題があったと思います。今でこそ当市もSNSをやっていますが、当時は広報紙と公式ホームページ以外の手段がなく、認知を高めるには力不足だったのかもしれません。
――それで、初年度のイベントは無事に終わったのですか。
はい。実は、私自身も農業体験に参加することにしたんです。農業は未経験だったので、「これを機に学ぼう」と考えました。
体験講座は週末に開催されていたので、1年間、週末はほぼ畑に通い、耕運機を動かしたりして手伝いながら勉強させてもらいました。実際、農業は楽しかったし、とてもいい野菜が収穫できました。また、その法人の人たちとも仲良くなりましたね。

2年目以降は起死回生、人気イベントに。
――イベントをやめよう、という考えは浮かびませんでしたか?
それはありませんでした。自分が体験してみて分かったことも多かったし、イベント自体はとてもいい内容だったので。
上司が言っていたのは、「専門的な知識や技術はJAなどがやってくれる。自治体にできることは、就農希望者に最初の入口を用意することではないか」ということ。スタート前からこうしたマインドがあったので、継続していけば認知度も増して、徐々に人が集まってくるのではと期待していたんです。
――佐藤さんたちのそうした期待は、その後実現したのでしょうか?
翌年以降、徐々に人数は増えました。勢いがついたのには様々な要因があって、農業が社会的に注目されはじめたことや、移住ブームなどが追い風になったようです。また、公式LINEなどのSNSを活用したプロモーションの強化もありましたし、もちろん受け入れ法人の協力も大きかったです。

見るまえに跳べ、きっと何とかなる。
――その時の経験は、佐藤さん自身にどのような影響を与えていますか?
知らないことがあれば、現場に飛び込んで勉強するのが一番だと確信しました。失敗を恐れていたら何もできなくなってしまうので、「失敗するかも、でもなんとかなる」というマインドで、まずはやってみることが大切だと思います。
――佐藤さん自身はチャレンジを恐れない性格ですか?
そうですね。新しい挑戦には、いつもワクワクします。そうした性格もあり、研修などはできるだけ受講するようにしています。今回の取材を受けたのも、同じような気持ちからです。
変化はきっと来る。その日に向けて準備を。
――ところで、自治体には失敗を共有する文化がないと聞きますが……。
確かに、私の知る限り、制度や仕組みとしては用意されていません。だからこそ、日頃から色々な人の話を聞くことが大切だと思います。
あとは、様々な研修の機会を逃さずに、積極的に参加することです。研修では新しい知識や考え方を身につけられるだけでなく、普段関わることのない他部署の職員ともコミュニケーションできます。
たとえ研修のテーマが今の仕事に直接関係ないとしても、いつか役に立つかもしれません。私もジャンルを問わず研修に参加しています。
――「失敗したくない」という職員に向けてメッセージを!
ある程度肩の力を抜くことが大切かもしれません。責任ある仕事をしていると、煮詰まったり思い悩んだりすることがあって、精神的に追い詰められてしまいます。時には「次の担当がもっとよくしてくれるかも」などと考えを変えるのもアリだと思います。
そして、分からないことは気軽に質問できる職場の環境が大事です。かくいう私も、たまにクサりそうになるときもありますし、やってみて「甘かった」と思い知らされることも多いですが(笑)。未来に期待をしつつ、日々頑張っています。

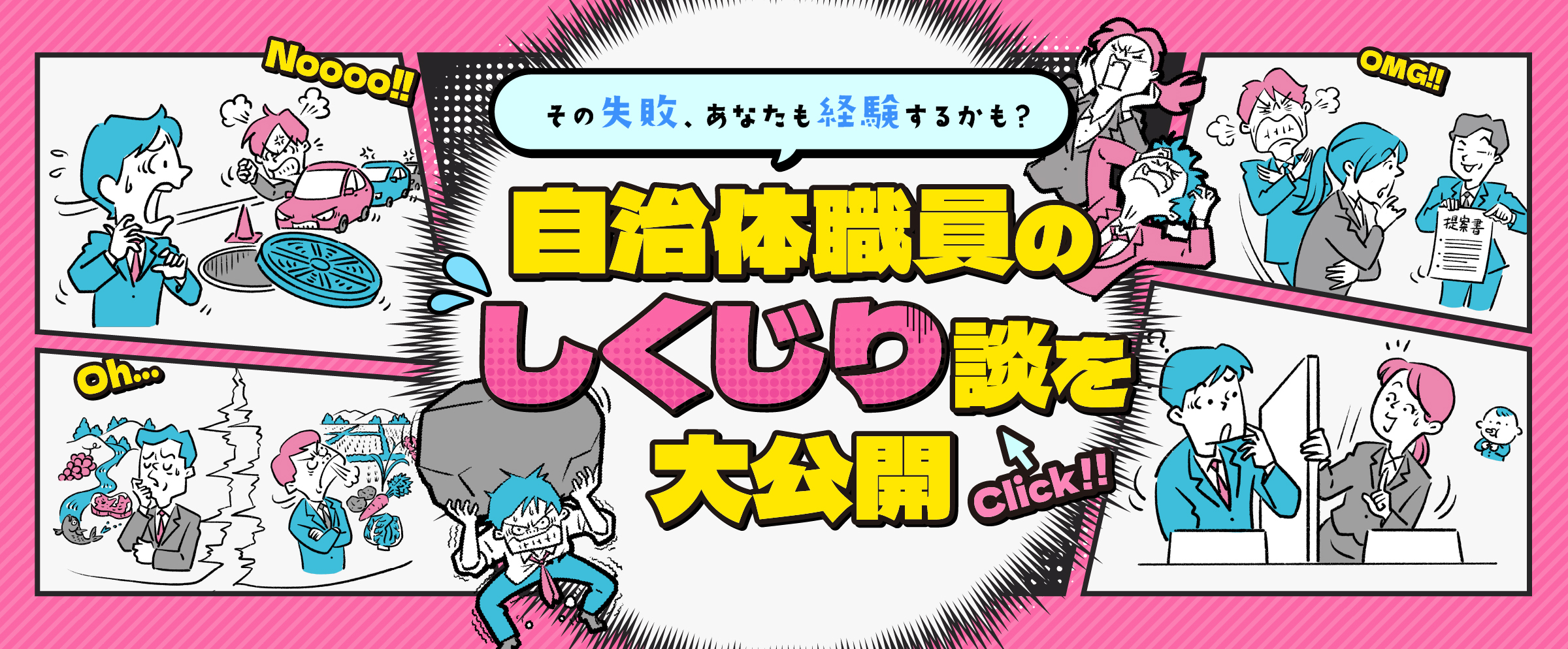
私のしくじり特集ページ一覧
#03 初めてのイベントなのに……私は農業体験講座でつまずいた。≫